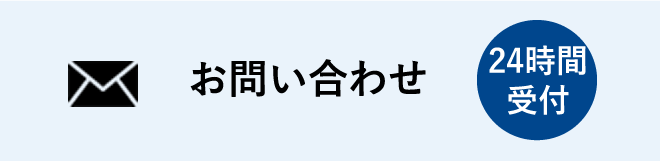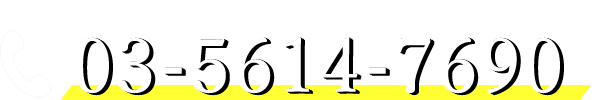当事務所の無罪事例【上訴審無罪】
傷害事件
事案の概要
キャバクラ店内での宴会中に、店長である被告人が、従業員の身体にアルコール消毒液をかけ,スプレーから噴射した可燃性ガスにライターの火を引火させ,その炎を噴射する暴行を加え,広範囲熱傷等を負わせたとされる事件。
争点
従業員(被害者)の身体になんらかの理由でアルコール消毒液が付着していたこと、被害者の体に火が付けられ、同人が熱傷を負ったことに争いはない。
被告人(店長)は、宴会に参加していてその場にはいたものの、火を付けたのは自分ではないと主張。被告人が犯人であるか否かが争点となった。
審理の内容
被害者は事件後に救急搬送されたが、その当時から「被告人に火をつけられた」と述べており、警察や検察の取調べでも、被告人に火を付けられた際の情景や、他の出席者の着席位置について、詳細に述べていた。嘘をつく動機もなかった。
他方で、他の出席者のうち2名は、被害者に火が付いていることが分かったとき、被告人は離れた席に座っていたと弁護人に対して述べた。また、被害者は飲み会の途中から嘔吐するなど、泥酔していたと述べた。
被害者の証言が信用できないこと、なぜ被害者が嘘をつくつもりはないのに、事実と異なる証言をしているかを明らかにする必要があった。
弁護活動のポイント
関係者への徹底的なヒアリングを行い、宴会の出席者全員から話をきいた。その結果、被告人以外の従業員が被害者に火を付けた可能性が高いと考えた。
被害者が事実と異なる証言をする理由を解明するために、事件直後から取調べの過程でしていた供述の経過を、供述心理学(※人が記憶に基づいて証言をする際の心理などを解明する学問。例えば自白が本心に基づくものか、幼児の証言が信用できるか、といった観点から法廷で意見が述べられることも少なくない)の専門家に相談し、検討してもらった。その結果、①被害者は当時泥酔状態にあり、いわゆるブラックアウトの状態にあったため、本来の記憶が残存していなくてもおかしくないこと②「無意識的転移」という現象により、実体験とは異なる詳細な記憶が後から作られることはあり得るところ、被害者は事件前の別の日に、被告人が他の店員にふざけてスプレー缶で火を噴射するシーンを見たことがあったから、この体験が無意識のうちに「事件当日、スプレー缶で被告人から火を噴射された」との記憶に刷り買った可能性があること③被害者が事件直後に「被告人に火を付けられた」と述べたのは、救急隊員や警察官に誘導されたり、答えを示唆されたからである可能性があること、が明らかとなった。
法廷では被害者、宴会に出席していた従業員の尋問だけでなく、被害者から事情を聴取した救急隊員や警察官の尋問が実施された。弁護人は被害者の記憶に重大な欠落があり、相当な酩酊状態であったことや、救急隊員や警察官からの事情聴取の方法が不適切であり、後から記憶がすり替わった(無意識的転移が生じた)ことを指摘する尋問を行った。供述心理学者も弁護側証人として出廷した。
判決の内容
①出席していた他の従業員の証言の信用性が認められ、これと食い違う被害者の証言の信用性は大きく減殺される。
②被害者が消防隊員に何らかの暗示や誘導を受け、それが事件直後の被害者の返答に影響を与えた可能性は否定できない。
③被害者の酩酊状況や供述状況に照らせば、記憶にはかなりの欠損部分があり、火がつけられた瞬間はそのことを認識していなかった可能性がある。他の機会に被告人から火を近づけられたという体験と混同している可能性も否定できない。結論として、被害者の証言の信用性には疑問がある。
判決日
令和元年5月16日
その他備考
第1審から弁護を担当していたが、第1審では有罪判決を受けた。控訴し、逆転無罪判決を受けた。第1審の裁判官は被害者の「具体的かつ迫真的な記憶が後から形成された記憶であるとは到底考えられない」と言い切っていたが、この結論は控訴審で否定されることとなった。
検察官は上告せず、確定した。
キャバクラ店内での宴会中に、店長である被告人が、従業員の身体にアルコール消毒液をかけ,スプレーから噴射した可燃性ガスにライターの火を引火させ,その炎を噴射する暴行を加え,広範囲熱傷等を負わせたとされる事件。
争点
従業員(被害者)の身体になんらかの理由でアルコール消毒液が付着していたこと、被害者の体に火が付けられ、同人が熱傷を負ったことに争いはない。
被告人(店長)は、宴会に参加していてその場にはいたものの、火を付けたのは自分ではないと主張。被告人が犯人であるか否かが争点となった。
審理の内容
被害者は事件後に救急搬送されたが、その当時から「被告人に火をつけられた」と述べており、警察や検察の取調べでも、被告人に火を付けられた際の情景や、他の出席者の着席位置について、詳細に述べていた。嘘をつく動機もなかった。
他方で、他の出席者のうち2名は、被害者に火が付いていることが分かったとき、被告人は離れた席に座っていたと弁護人に対して述べた。また、被害者は飲み会の途中から嘔吐するなど、泥酔していたと述べた。
被害者の証言が信用できないこと、なぜ被害者が嘘をつくつもりはないのに、事実と異なる証言をしているかを明らかにする必要があった。
弁護活動のポイント
関係者への徹底的なヒアリングを行い、宴会の出席者全員から話をきいた。その結果、被告人以外の従業員が被害者に火を付けた可能性が高いと考えた。
被害者が事実と異なる証言をする理由を解明するために、事件直後から取調べの過程でしていた供述の経過を、供述心理学(※人が記憶に基づいて証言をする際の心理などを解明する学問。例えば自白が本心に基づくものか、幼児の証言が信用できるか、といった観点から法廷で意見が述べられることも少なくない)の専門家に相談し、検討してもらった。その結果、①被害者は当時泥酔状態にあり、いわゆるブラックアウトの状態にあったため、本来の記憶が残存していなくてもおかしくないこと②「無意識的転移」という現象により、実体験とは異なる詳細な記憶が後から作られることはあり得るところ、被害者は事件前の別の日に、被告人が他の店員にふざけてスプレー缶で火を噴射するシーンを見たことがあったから、この体験が無意識のうちに「事件当日、スプレー缶で被告人から火を噴射された」との記憶に刷り買った可能性があること③被害者が事件直後に「被告人に火を付けられた」と述べたのは、救急隊員や警察官に誘導されたり、答えを示唆されたからである可能性があること、が明らかとなった。
法廷では被害者、宴会に出席していた従業員の尋問だけでなく、被害者から事情を聴取した救急隊員や警察官の尋問が実施された。弁護人は被害者の記憶に重大な欠落があり、相当な酩酊状態であったことや、救急隊員や警察官からの事情聴取の方法が不適切であり、後から記憶がすり替わった(無意識的転移が生じた)ことを指摘する尋問を行った。供述心理学者も弁護側証人として出廷した。
判決の内容
①出席していた他の従業員の証言の信用性が認められ、これと食い違う被害者の証言の信用性は大きく減殺される。
②被害者が消防隊員に何らかの暗示や誘導を受け、それが事件直後の被害者の返答に影響を与えた可能性は否定できない。
③被害者の酩酊状況や供述状況に照らせば、記憶にはかなりの欠損部分があり、火がつけられた瞬間はそのことを認識していなかった可能性がある。他の機会に被告人から火を近づけられたという体験と混同している可能性も否定できない。結論として、被害者の証言の信用性には疑問がある。
判決日
令和元年5月16日
その他備考
第1審から弁護を担当していたが、第1審では有罪判決を受けた。控訴し、逆転無罪判決を受けた。第1審の裁判官は被害者の「具体的かつ迫真的な記憶が後から形成された記憶であるとは到底考えられない」と言い切っていたが、この結論は控訴審で否定されることとなった。
検察官は上告せず、確定した。